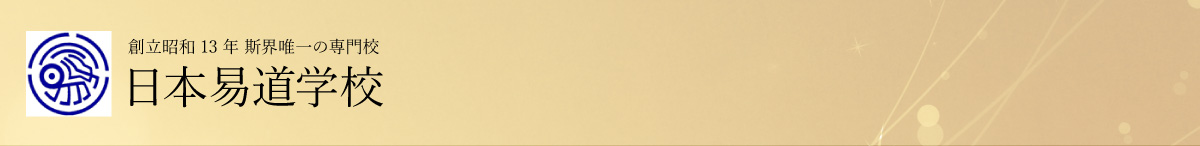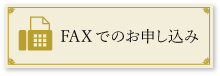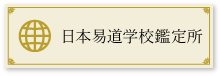コトタマ
「鏡の中の虚像」 2021/01
兆候(兆し)はむしろ気射し(エネルギーの始動)とした方が、日本語のキザシに近いと思われます。音図構造ではカ語を起点としてキザシがあり、そこからあらゆるコトバが展開していることは、日本のカミの意義を考えるのに大変重要です。
日本人が日頃、カ語をどのような場合(現象)に使うか、考えてみましょう。
かすか(幽)かすみ(霞)かげ(影)かげろう(陽炎)かぜ(風)など。
このカ語群の集合から帰納すると、存在することは肯定できますが、はっきり形として認識できない現象であり、カミも勿論、この語群に属することは明らかです。
存在は肯定できるが、明確に認識できないという意味を、日常的によく使われる「本当か」、「そうなのか」という?的に使われるカ語が、最もよくその語位相を表現しています。カ語が疑問符になることです。
目に見えぬカ語の場に、まずキザシがあって、あらゆる現象事物(言=事)が現われるということは、万物はその創造以前に、カ語に内蔵されていることであり、それは「あれが何々した」、「これらが私のです」という、所属や所有を意味するカ語にもなっています。
まさにカミのカ語は「無から有を生じる目に見えぬ万物創造のポテンシャルな場」と規定することができます。それは天地という三次元的な視野を超えた場です。ミ語(啓運第411号のコトタマに記述)は現われるという意味を持ちます。
ここで述べたいことは、日本語は概ねその形より質が、原則であるということです。ここでは神話的にも私たち日本人に関わり深い、カガミのことを考えてみたいと思います。
現代の鏡は、ガラス板の裏にアマルガムを塗布したものですが、古代では青銅、鉄で作られ、その形もさまざま見られます。しかしその青銅や鉄製以前には水鏡であったことは、おそらく人類に共通であったことだろうと思われます。
静かな湖面に、くっきりと逆さに映る山々、そして足元には自己の姿形が鮮やかに映されています。現在では、それは光の反射に過ぎないことは、科学常識ですが、そんな科学常識をもたぬ太古の人々は、どんなに驚きの眼で見詰めていたことでしょう。しかも水面に少しでも波風が立てば、自己の姿はたちまち消えてしまいます。その現象に太古の人々が、いかに驚きかつ感動したかは、現代人の想像以上であったと思われます。
そこに存在は肯定できるが実体はない。その映像がカガミです。どんなに立派な外形をもつ鏡でも、それが錆びて何も写らなかったら、もうカガミとはいえません。ただの錆びた鉄板や曇ったガラスに過ぎません。日本語は形よりもその質をいいます。
形ある存在は虚像にすぎず、本当の自分はその背後あります。それは後の宗教的形式を生む素地であり、音図でカミにあたり、人類のカミ観念の芽生えです。